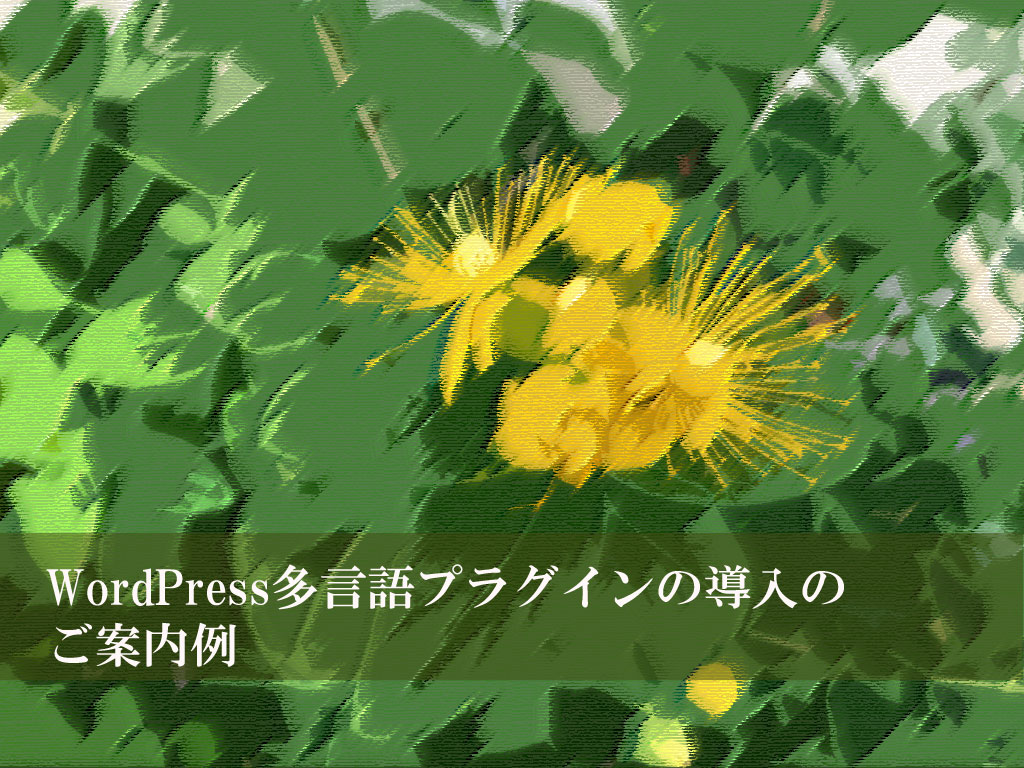プラグインの選定や設定方法を誤ると、SEOへの悪影響や更新作業の煩雑化といった問題が発生する可能性もあります。また、多言語プラグインを設定して、英語と中国語のページ追加するよう設定していただきたい。デザインは日本語ページをコピーで大丈夫です。グローバルメニューの七五三と、成人式だけ要りません。なのでグローバルメニューは少しだけ変えないといけないですね、自分で文字を変える場合と流し込んでいただく場合。
- Bogo
- Polylang
- Translate WordPress with GTranslate
- Google Website Translator
- WPML
- Multisite Language Switcher
- MultilingualPress
- Multilanguage by BestWebSoft
- WPGlobus
- Sublanguage
複数言語に対応しておりますので、「どの言語のサイトから制作したらよいのか迷っている」という方には、どの言語からのアクセスが多いのかを分析した上で、その後の外国語サイト制作のご提案可能。また、通常の日本語サイト制作のご提案時に、「多言語サイトも無料で作れます」というお客様へのご提案のフックとしても、お使い頂いております。中小企業様から大手企業様、自治体まで、日々多くのご利用企業様が増え、お喜びの声を頂いております。
Google翻訳などの機械翻訳のみを使うと、内容の精度が低下し、信頼性を損ないます。できるだけプロ翻訳者かネイティブチェックを入れるのが理想です。多言語化の対象範囲を決めると良いと考えます。すべてのページを翻訳する必要はありません。まずは「企業情報」「サービス案内」「お問い合わせ」など、必要最小限のページから始めるのが現実的です。
多言語サイト制作を進める際に重要になるのは、翻訳作業そのものだけでなく、運用を想定した設計です。たとえばプラグインで日本語ページを複製して英語や中国語ページを作成すること自体は技術的には難しくありません。しかし、公開後に更新が発生するたびに各言語ページを同時に修正していく必要があります。メニューの項目を一つ削除するだけの変更であっても、日本語・英語・中国語のすべてに反映しなければならないため、制作段階から更新作業の流れを意識しておくことが欠かせません。最初にきちんと運用フローを設計しておけば、のちのちの負担を大きく軽減することができます。
また、言語選択プラグインの違いによって管理画面の扱いやすさやSEOへの影響も変わります。WPMLのように実績が豊富で大規模サイトでも安定して使えるプラグインもあれば、Polylangのように軽量でシンプルに複数言語を管理できるものもあります。一方で、Google Website TranslatorやGTranslateのように機械翻訳をベースにした即時多言語化を実現するものは、スピード感はありますが、翻訳の品質やSEO評価の観点では慎重にならざるを得ません。特に検索エンジンに対して別々のURLを発行してインデックスさせるかどうかという部分は、集客の成果に直結します。
中小企業のお客様の場合、限られた予算やリソースで運用することが多いため、すべてのページを翻訳して公開するのではなく、優先度の高いページから着手するのが現実的です。会社概要やサービス説明、問い合わせフォームといったコア情報さえ多言語化しておけば、海外からの問い合わせやビジネスチャンスを逃さずに済みます。逆に、ニュースやブログ記事などをすべて翻訳しようとすると、コストも手間もかかりすぎて更新が滞り、結果的にサイト全体が放置されるリスクが出てきます。
翻訳の方法についても、単純にGoogle翻訳で流し込むだけでは読み手に不自然さが残ってしまいます。ビジネス利用を前提とするなら、専門用語のニュアンスを正確に伝えることが信頼性の担保につながりますので、可能であればプロの翻訳者に依頼するか、最低限ネイティブのチェックを通すことをおすすめします。最近ではクラウド翻訳サービスやオンラインのネイティブチェックサービスも増えており、従来より低コストで質を担保する方法も広がっています。こうした選択肢をうまく組み合わせることで、費用を抑えながらも実用的な多言語サイトを構築できます。
さらに考慮すべき点は、各言語における検索需要です。多言語化を検討するお客様の中には「どの言語から始めればよいのか分からない」という方も多くいらっしゃいます。その場合には、既存のアクセス解析を用いて海外からの流入がどの国や地域から多いかを確認することが効果的です。例えば英語圏からのアクセスが中心であればまず英語版を整備し、中国語圏からのアクセスが増えているなら次に中国語版を追加する、といった段階的な進め方が合理的です。すべての言語に同時対応するのではなく、アクセスデータに基づいて優先順位を付けていくことで、コスト効率の良い展開が可能になります。
また、SEOの観点から見ると、多言語ページのURL構造も重要なポイントです。サブディレクトリ形式で「/en/」「/cn/」と分けるのか、サブドメイン形式で「en.example.com」「cn.example.com」とするのか、あるいは完全に別ドメインで展開するのか。それぞれにメリットとデメリットがありますが、更新管理のしやすさや既存ドメインの評価を継承できるかどうかを考慮すると、多くの場合はサブディレクトリ形式が現実的です。検索エンジンが言語ごとのコンテンツを正しく認識できるように、hreflangタグの設定も欠かせません。これを怠ると、同じ内容を複数言語で公開していると見なされ、重複コンテンツのリスクにつながる可能性もあるため注意が必要です。
中小企業や自治体においては、多言語化の導入は単なる「翻訳ページの追加」にとどまりません。海外との取引機会を広げたり、観光誘致や留学生募集などに直結する戦略的な取り組みとなります。たとえば自治体が外国語ページを整備することで、海外からの観光客が安心して情報を取得できるようになり、地域の経済にプラスの効果をもたらすことが期待できます。同様に、製造業の中小企業が英語版サイトを持つことで、これまで国内にとどまっていた販路を海外に広げるきっかけを作ることができます。このように、多言語対応は単なるオプションではなく、事業戦略の一環として位置づけるべきものです。
一方で、多言語化には避けて通れない課題も存在します。例えば、問い合わせ対応の言語です。英語や中国語のページを用意したとしても、実際に問い合わせが入った際に社内で対応できる人材がいなければ、せっかくのビジネスチャンスを逃してしまうことになります。そのため、翻訳やページ制作だけでなく、運用後の体制をどう整えるかまで考えておく必要があります。外部の翻訳会社と連携したり、社内で英語や中国語を扱えるスタッフを育成するなど、段階的に体制を整えていくことが望ましいでしょう。
こうした課題を踏まえると、最初から完璧な多言語サイトを構築しようとするのではなく、優先ページに絞ってテスト的に公開し、その成果を見ながら範囲を広げていく方法が適しています。日本語ページをコピーしたデザインをベースにしつつ、文字情報だけを差し替えることで、初期段階の負担を最小限に抑えることができます。そして実際にアクセスや問い合わせがどの程度発生するのかを確認し、効果があると判断できたら追加の翻訳を進める。このように段階を踏むことで、コストをかけすぎずに効果を検証しながら進められるのです。
総じて、多言語サイトの制作と運用は、単なる翻訳作業ではなく、SEO、デザイン、運用体制、そして企業のビジネス戦略に直結する包括的な取り組みといえます。どのプラグインを選ぶか、どのページから翻訳を始めるか、翻訳の品質をどう担保するかといった細部の選択が、公開後の成果に大きな影響を与えます。海外からのアクセスや問い合わせの増加を見込んでいる企業であれば、将来の更新性や体制づくりまで含めて戦略的に設計していくことが、成功のための第一歩になるのです。