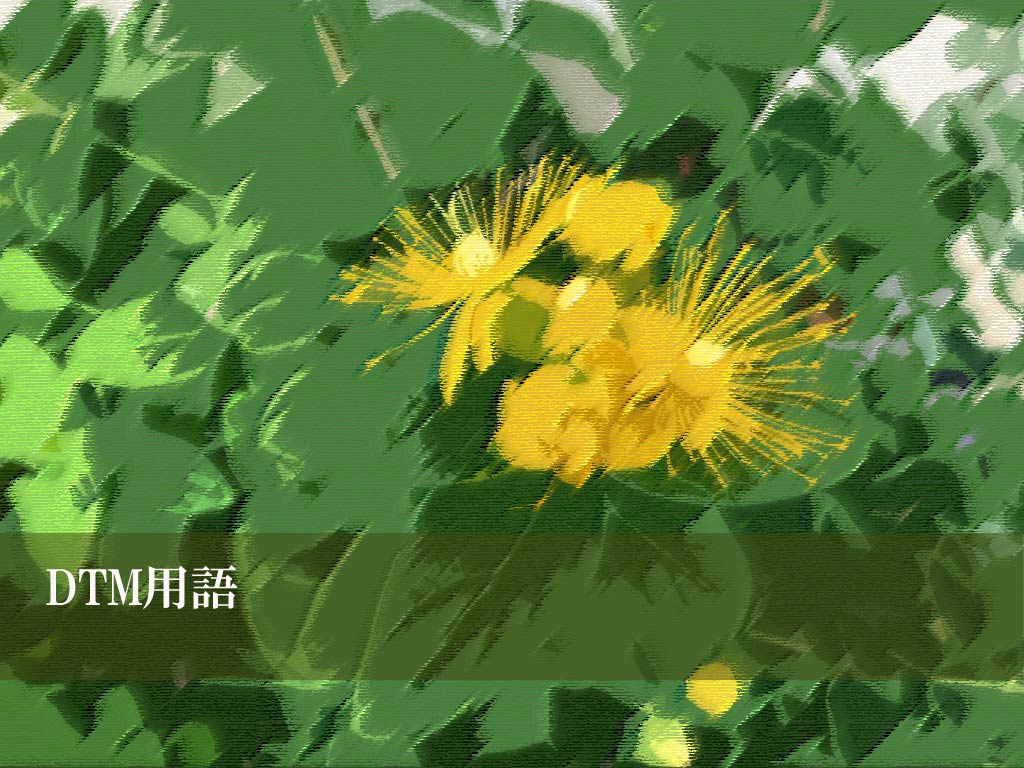DTM用語、デスクトップミュージック(desktop music)用語辞典
DTM用語集
デスクトップミュージック(desktop music)、いわゆるDTMは、パーソナルコンピュータを用いて音楽制作を行う概念として1980年代後半から1990年代初頭にかけて普及し始めました。
その背景には、MIDI(Musical Instrument Digital Interface)の標準化、シーケンサーソフトの進化、そしてパソコン自体の演算能力向上が大きく関わっています。DTMの歴史を振り返ると、ハードウェア中心からソフトウェア中心へ、さらにクラウドやAIを組み込む現在へと段階的に移行してきたことが理解できます。
初期のDTMは、ローランドのMT-32に代表される外部音源モジュールをパソコンに接続し、シーケンサーソフトウェアで打ち込みを行うスタイルが主流でした。
当時はMIDIインターフェースが必須であり、音色エディットにはシステムエクスクルーシブメッセージ(SysEx)を駆使する必要がありました。オーディオの扱いは困難で、波形編集やマルチトラックレコーディングは専用のハードディスクレコーダーに依存していました。
1990年代半ばになると、WindowsやMacintoshの普及に伴い、CubaseやLogic、CakewalkといったDAW(Digital Audio Workstation)が一般化します。これにより、ピアノロールエディタ、イベントリスト、ステップ入力といったシーケンス手法が標準化され、MIDIデータの可視化と編集が容易になりました。また、Sound Blasterなどのサウンドカードが普及したことで、PCM音源の利用やオーディオトラックとの同期が実現し、MIDIとオーディオのハイブリッド制作が可能となります。
2000年代に入ると、VST(Virtual Studio Technology)によるソフトウェア音源やエフェクトプラグインが急速に発展しました。従来はラックマウント型のハードウェアでしか実現できなかったシンセサイザーやコンプレッサー、リバーブがソフトウェア化され、プラグインエコシステムとして統合されました。
ソフトシンセによりサンプルベース音源や物理モデリング音源の表現力が飛躍的に高まり、サンプラーによるループベースの制作も加速します。この時期、オーディオインターフェイスの低価格化とASIOドライバによる低レイテンシー処理もDTM普及を後押ししました。
さらに2010年代以降は、DAWの機能が統合的に進化し、マルチトラックレコーディング、ミキシング、マスタリングまでワンストップで完結できるようになりました。Ableton Liveのようにリアルタイム性を重視したクリップベースのシーケンスや、FL Studioのようなパターンベースの制作スタイルが浸透し、音楽ジャンルや制作手法そのものにも影響を与えています。ソフトシンセではFMシンセシス、アナログモデリング、ウェーブテーブルシンセシスなど多様なアルゴリズムが進化し、エフェクト面でもコンボリューションリバーブやマルチバンドコンプレッサーが標準化しました。
現在のDTMは、クラウドベースのコラボレーション、AIによる自動アレンジやマスタリング、MPE(MIDI Polyphonic Expression)による表現力拡張など新たなステージに入りつつあります。ハードウェアコントローラーとソフトウェアを連携させたハイブリッド制作も定着し、フィジカルな操作感とデジタルの柔軟性が融合しています。
つまり、デスクトップミュージックの歴史は、MIDIの誕生からDAWの進化、プラグインの普及、クラウドとAIの導入という技術革新の連続であり、音楽制作の民主化を象徴する存在となっているのです。