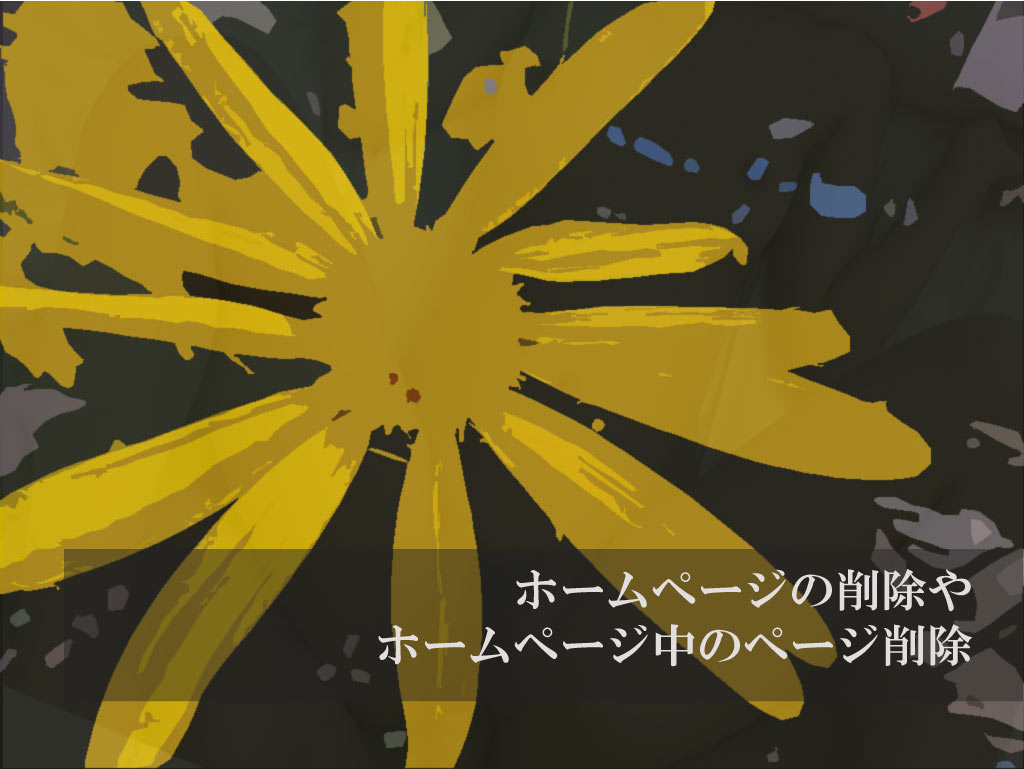ホームページの削除やホームページ中のページ削除について。現在公開しているホームページの情報が古くなり公開状態にしたくない場合など、ホームページ自体を削除したい、非公開にしたい、一部のページを削除したいという場合があります。ホームページ(ウェブサイト)を削除する場合、静的HTMLサイト、WordPress等のCMS等そのホームページの仕様によって削除の方法が多少異なります。
静的HTMLサイトの削除、WordPressサイトの削除
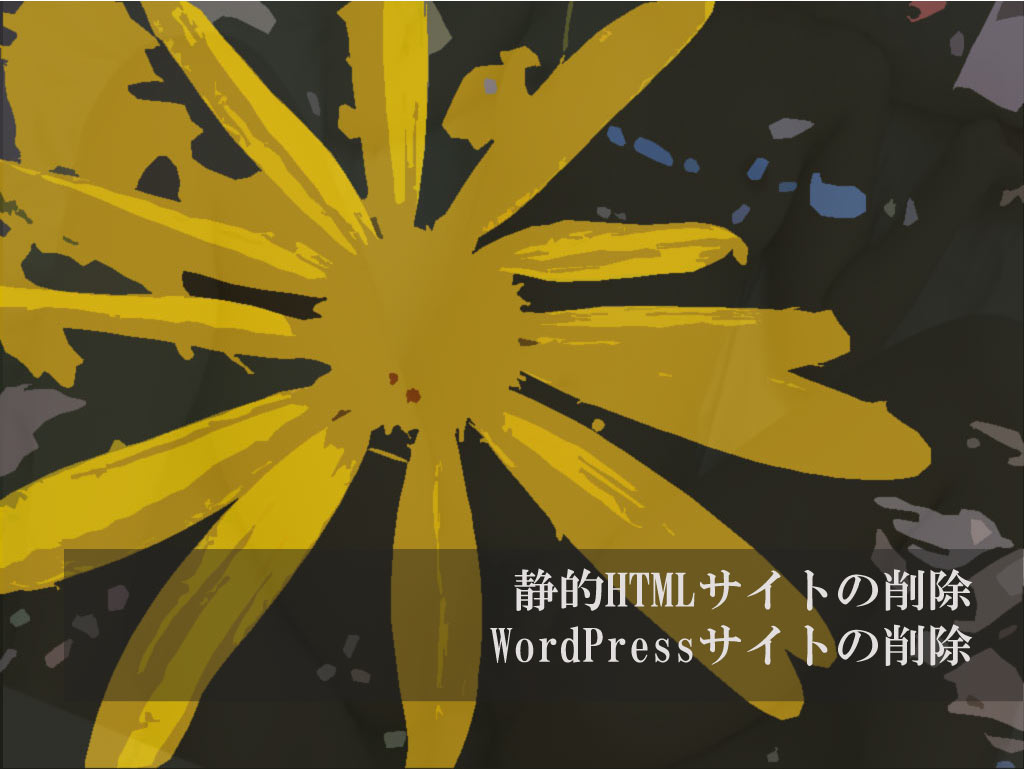
静的HTMLサイトを削除する場合、基本的にはFTP接続やファイルマネージャによってサーバーにアクセスし、対象ドメイン下にあるHTMLファイル群など、対象ファイルを全て削除します。
WordPress等のCMSを削除する場合、基本的にはサーバーコントロールパネル等で、対象CMSを削除します。
WordPressなどのCMSは以下の2要素で構成されています。
① サーバー上のファイル群(php、画像、CSSなど)
② データベース(主にMySQL)
単にファイルを削除しただけでは、データベースに投稿や設定情報が残り続けるため、完全な削除を行いたい場合は、両方の削除が必要です。削除前の注意点としてバックアップの取得をしておいたほうが無難です。削除後に「やっぱり戻したい」となっても、元に戻せないため、ファイル・データベースともに事前バックアップを取ることが必須です。サーバーやデータベースを複数サイトで共有している場合、誤って他のデータまで消すリスクがあります。対象CMSが独立しているかを必ず確認しましょう。
WordPressのファイル削除手順
FTPソフトで手動削除
FTPソフトでサーバーに接続
WordPressがインストールされているディレクトリ(例:/public_html/)を確認
該当フォルダごとすべて削除(wp-content, wp-admin, wp-includesなど)
レンタルサーバーのファイルマネージャーで削除
サーバー会社の管理画面にある「ファイルマネージャー」から対象ディレクトリを削除します。
データベースも削除する必要がある
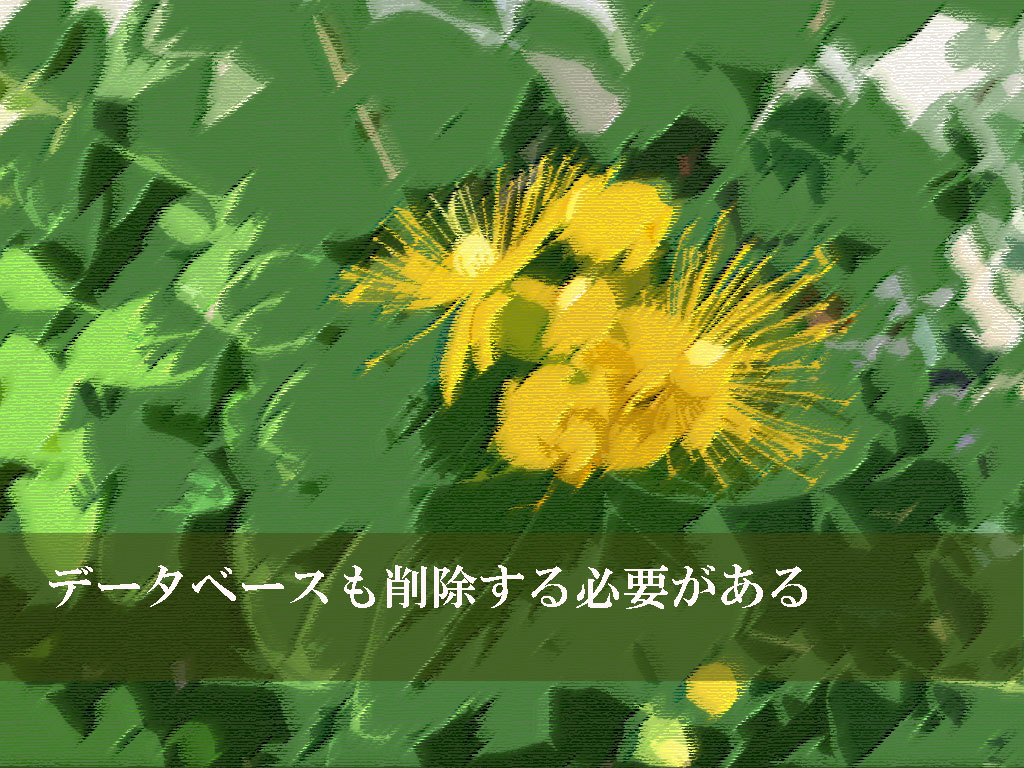
対象ドメイン内のファイルは全て削除されますが、対象WordPressに利用されていたデータベースも削除する必要があります。このデータベース削除に関しては、サーバーコントロールパネル等で別途削除作業を行う必要があります。
データベースの削除手順
どのデータベースを使っているかを確認
wp-config.phpの中の記述を確認し削除対象のデータベース名を確認してから削除します。
一部のページを削除
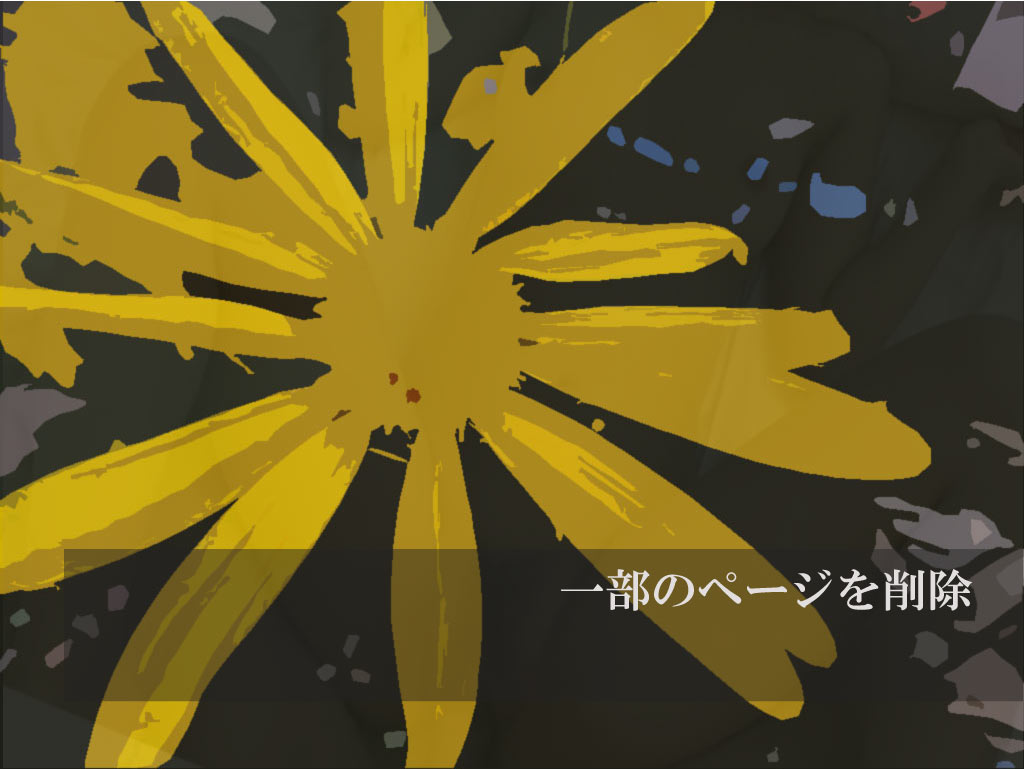
ホームページ中の一部のページのみを削除する場合もホームページの仕様によって方法は若干異なります。
静的HTMLサイトの一部のページを削除する場合、基本的にはFTP接続等により、対象となるHTMLファイルやphpファイルを削除します。WordPressサイト等のCMSサイトの一部のページを削除する場合、CMS管理画面内でページ削除作業を行います。WordPressであれば、基本的には投稿や固定ページ、カスタム投稿の編集画面からページ削除を行います。しかしながら、テーマ内で特別に作成されたなページである場合は、テーマファイルの修正やFTP接続によって対象ページに関するファイルを削除します。
なお、こうして一部のページのみを削除した場合は、一般的にメニューやリンクの修正が必要になります。
ページを削除するという決断を下す前に、将来の影響を見越した戦略的な判断を伴うことが非常に重要です。特定のページを削除するのは、単なる整理作業ではなく、SEO、ユーザー体験(UX)、ブランド信頼性、そして将来的なコンテンツ資産という観点からのリスクと機会を慎重に評価する必要があります。
削除のリスクとSEOへの影響
まず、ページ削除を行うと SEO的なマイナス影響が出る可能性があります。特にそのページが過去に被リンクを獲得していた場合、それらのリンクは失われ、ドメイン全体の評価低下につながる可能性があります。さらに、削除されたページに対して検索エンジンのクローラーがアクセスを続けていた場合、404エラーが多数発生し、クローラビリティ(巡回効率)にも悪影響を及ぼす可能性があります。
これを避けるためには、301リダイレクトを適切に設定することが基本です。具体的には、削除対象のページを、関連性の高い他のページ(例えば、カテゴリーページや代替コンテンツ)に恒久的にリダイレクトすることで、リンクエクイティ(被リンクの価値)をなるべく維持しつつ、ユーザーが「ページがない」状況で途方に暮れないようにします。
コンテンツアーカイブと再利用の戦略
また、ページを完全に削除するのではなく、**アーカイブ(別領域保存)**しておく選択肢も非常に有効です。過去の記事や解説コンテンツには、時間の経過とともに変化する情報と残すべき情報があります。たとえば、技術トレンドや過去のニュース記事など、時代が変わっても「歴史的な価値」「参考資料」としての意味を持つものは、アーカイブとしてキープしておくことで、中長期的な資産になります。
さらに、アーカイブしたコンテンツを リライト(書き直し)・再構築 して再公開することで、新しいSEOキーワードへの対応やトレンドへの適応が可能です。これにより、削除リスクを抑えつつ、既存コンテンツを再活用して集客基盤を強化できます。
ユーザー体験 (UX) の観点からの配慮
ページを削除する際には、ユーザー体験にも気を配る必要があります。削除されたページに対して何らの代替措置もなく404ページを表示させるだけでは、ユーザーにとってストレスが大きくなります。これを防ぐために、カスタム404ページの作成が望ましいです。
カスタム404ページには、削除されたページの説明、代替コンテンツへのリンク(ブログ、カテゴリ、サイトマップなど)、または検索ボックスを設置して、ユーザーが次の目的地をすぐに見つけられるように誘導しましょう。これにより、離脱を最小限にし、ユーザービリティを維持できます。
削除判断のプロセス設計
ページ削除を単発の作業で終わらせず、 削除流程 (ワークフロー) を設計しておくことが望まれます。具体的には以下のステップを検討すべきです:
削除候補ページの洗い出し:過去のアクセス分析、被リンク数、更新頻度、重要度などを基に候補をリスト化
影響分析:SEO、トラフィック、ユーザー遷移、CV(コンバージョン)への影響を評価
代替コンテンツの設計:リダイレクト先や新規ページ、アーカイブ方式の検討
実施タイミングの決定:大きなイベントやキャンペーンに合わせて実施し、影響を最小化
監視と検証:リダイレクト設定後のアクセス挙動をモニタリングし、必要に応じて調整
運用ルール化:定期的な「削除候補見直し」「古いコンテンツのアーカイブ」「リライト計画」をガバナンス化
保守・運用視点からの長期価値
ホームページを長く運用するうえでは、コンテンツの ライフサイクル管理 を意識することが重要です。すべてのページを永続的に保持することはコスト高となる場合がありますが、だからといって無秩序に削除するのはリスクがあります。ライフサイクル管理を通じて、「どういうタイミング、どういう条件で削除またはアーカイブするか」の基準をあらかじめ設けておくことで、サイトのクオリティと収益性を両立させられます。
例えば、3年アクセスがないページ、SEO価値が低下しているページ、またはサービス終了・古いプロモーションコンテンツなどは、 アーカイブ or 削除 の判断対象になります。一方で、定期的にトラフィックを生み出すページ、新規のお問い合わせをしっかり生んでいるページはそのまま運用するか、リライトを通じて更新を続けて資産化するのが良いでしょう。
削除ではなく整理・改善という視点への転換
最終的に、ページ削除を単なる「削除」としてではなく、 整理および戦略的改善 のフェーズと捉えることが望まれます。削除が必要なケースもあるかもしれませんが、それよりもまずは整理(アーカイブ)・再評価(リライト・統合)・改善(導線やコンテンツ構造の最適化)によって、ホームページ全体の価値を引き上げることが理想です。
削除判断は確かにコストカットや情報整理の手段として有効ですが、それが常に最善とは限りません。時には残すことで長期的な資産になるコンテンツもあるのです。
削除を行う際には、そのリスクと利点を冷静に比較し、慎重かつ戦略的にアプローチすることが、Web集客・SEO・ユーザー体験を見据えた最適解につながります。
以上を踏まえて、ページ削除をメンテナンス作業と捉えるのではなく、 長期戦略の一部 として位置づけて考えていただきたいと思います。ページ削除・整理によって生まれる空間には、新たなコンテンツ戦略や導線改善の余地があり、これを機会にホームページ全体の価値を高めるステップとして設計できるかが重要です。