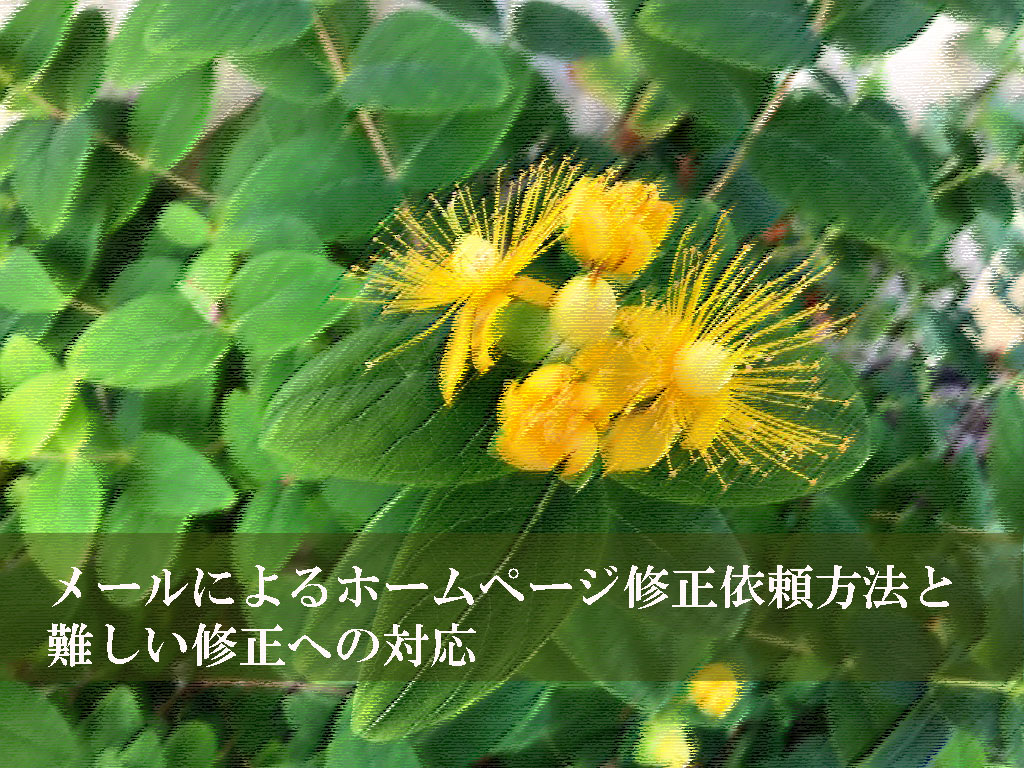メールによるホームページ修正のご依頼方法や修正内容のご連絡方法など、ご依頼にかかる具体的な内容と「難しい修正への対応」を掲載させていただきます。メールによるホームページ修正依頼方法のうち、文では伝えにく部分は、修正対象の既存ページをスクリーンショットしたり、PCの純正ツールでキャプチャ画像(切り取り画像)を生成して、修正内容を画像内に書き込むという方法もあります。
「ホームページの修正依頼をする時も、メール文の場合どうやって伝えたらいいかわからない」という場合の解決策として画像を利用した連絡方法があります。こうした内容に触れていきます。
また、難しい修正への対応、他社でホームページ修正依頼を断られるような修正内容への対応についての概要についても掲載いたします。
メールによるホームページ修正依頼方法の全体
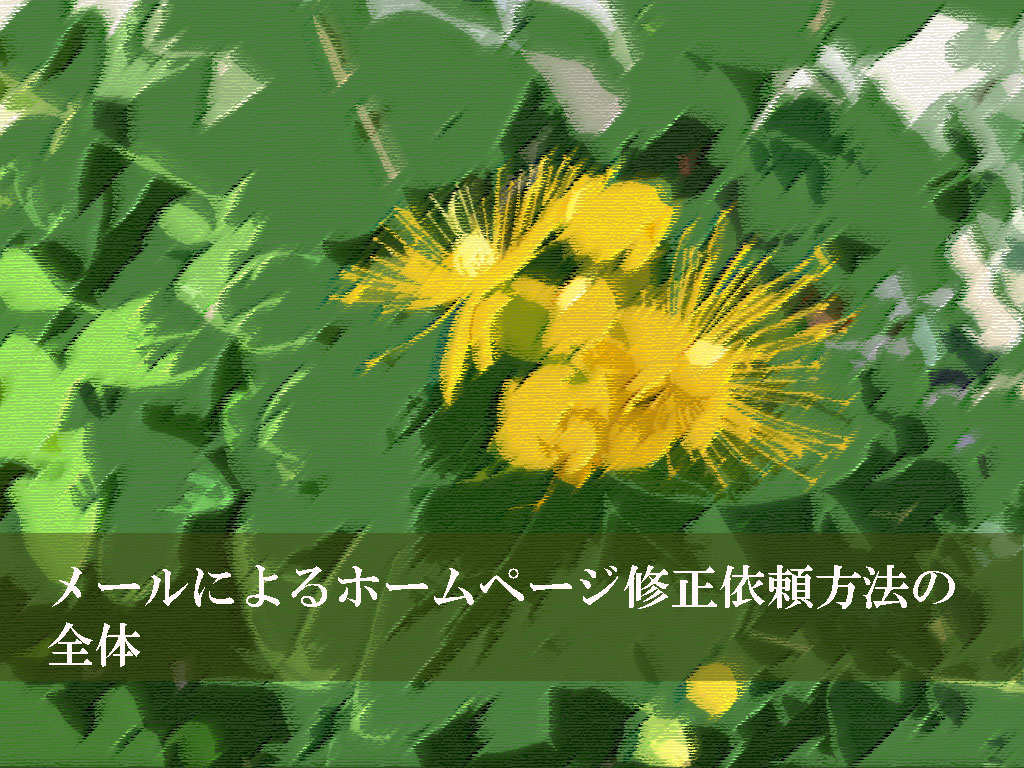
ホームページ修正・ホームページ更新のご依頼方法の全体像ご案内です。ホームページ修正依頼時の修正内容のご連絡方法は、原則メール文でご連絡いただいております。修正するページのURL、修正の内容をご連絡ください。
お問い合わせフォーム等からご連絡いただき、最初に修正するホームページのURL(修正対象ページのURL)と、修正にかかるご要望(修正内容)をお伝え下さい。修正対象ホームページならびに修正対象となる具体的なページを確認させていただき、ご希望の修正内容を把握させていただきます。
折り返しホームページ更新・修正にかかる概算のお見積を添えてご連絡させていただきます。
その際のご返信において、差し替える文章や画像、細かなご要望などをご送付ください。
サーバー内部を確認しなくてもサイト表示のみでお見積りできる場合は、そのままお見積額のご案内をさせていただきます。WordPress等の修正でお見積りのために現状把握が必要な場合は「WordPress管理画面の確認」をさせていただく場合があります。詳しいをお見積もりをご希望の場合は、この時に管理画面ログイン情報をご連絡ください。
実際のホームページ修正作業の際には、現在ご利用のホームページを修正するためのサーバーコントロールパネルログイン情報、FTP接続情報等の「サーバー接続情報」もしくは、WordPressログイン情報などが必要となります。
なお、ホームページの修正に関する各種ログイン情報、WebサーバーのFTP情報やWordPress等のログイン情報が不明な場合はお取り扱いできない場合がございますが、調査方法等につきましてご案内させていただくことも可能です。
スクリーンショット(キャプチャ)を使ったホームページ修正内容の連絡
を使ったホームページ修正内容の連絡.jpg)
メールによるご連絡時に、メール文章での表現が難しい場合は、スクリーンショット(キャプチャ)等の画像を送付いただとご連絡がスムーズになります。
修正対象ページをスクリーンショット(キャプチャ)で保存いただき、修正箇所に印を入れていただく方法があります。また、該当ページをプリントアウトした上で手書きで修正内容を記載いただいたき、そのプリントを画像としてお送りいただく方法もあります。
スクリーンショット・キャプチャの生成と文字入れ
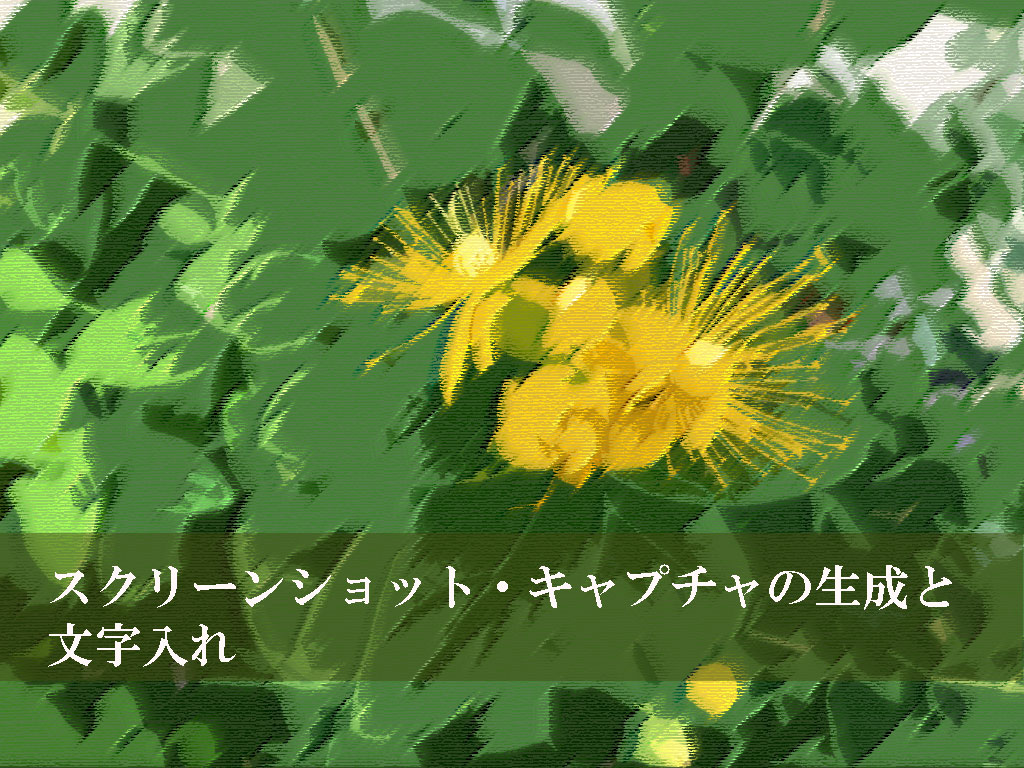
Windows10以降であれば「切り取り&スケッチ」を利用することで、画面の切り取りが可能です(それ以前のWindowsであれば「Snipping Tool」というツールがあります)。切り取りたい画面を表示させておき、「スタートボタン」をクリックし、「すべてのアプリ」から「切り取り&スケッチ」をクリックして起動してキャプチャ画像を生成します。
「切り取り&スケッチ」では、ボールペン、鉛筆、蛍光ペンなどの線の種類を選択して線を描画することができます。それぞれのアイコンをクリックすると、線の色や太さを選ぶことができます。この機能を利用すれば、切り取った画像に線を描くことができるため、文字入れをしていただくことが可能です。「ホームページ修正依頼の連絡でメール文では伝えにくい」という場合は、こうした機能を利用してみてください。
修正が難しく他社でホームページ修正依頼を断られる修正内容への対応
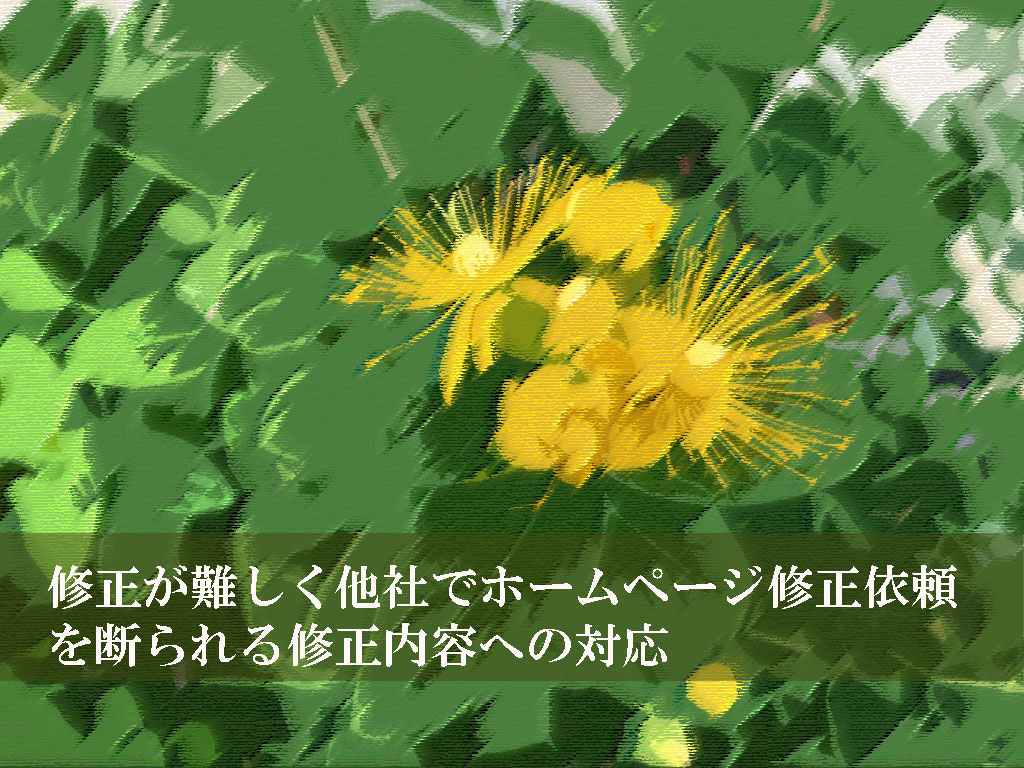
修正が難しく他社でホームページ修正依頼を断られるような修正内容のパターンはいくつかあります。原因は大きく分けると以下のようなものになります。
- 複雑な構造で設計されているサイト
- 修正箇所を発見することが困難
- phpとデータベースで設定されており、データベースにアクセスすることができない
- 加工前素材がないため画像加工が困難
- 現行の各種バージョンと開発時の設計が噛み合わず不具合ある
- 独自開発CMSによる該当箇所の修正制限
他社でホームページ修正依頼を断られるような修正内容への対応として、大きく分けると次のような方法があります。
- 強制的に修正する
- 現状の機能を一旦廃止し、再度構築する
- 求める結果から逆算して全く新しい方法を導入する(サイト移転やサイトの再構築を含む)
ホームページの運用が長期化してくると内容の更新や機能追加だけでなく修正が必要になる場面も増えてまいります。しかし実際には、依頼したはずの修正が断られてしまったり、「対応不可」とされてしまったりすることもあります。これは、単にホームページ制作会社側の都合によるものだけではなく、技術的・構造的な難易度や契約上・権利上の制約が影響している場合が多く依頼される方としては見えにくいものとなっています。ホームページ制作会社やWeb制作者が対応を断る代表的なパターンを具体的に取り上げ、その背景と対応策について触れていきます。ホームページの修正が断られる理由は、「手間がかかるから」という単純な話ではなく、その修正の裏側にある技術的・構造的な制約、そして管理体制の欠如が要因であることがほとんどです。制作者側としては「責任の所在が不明確」「作業リスクが高い」「根本解決にならない」という懸念を抱くこともあり、安易に請け負うことを避けるのです。もし修正を実施する場合は、まずはサイトの現状把握とデータ整理、そして「修正」なのか「リニューアル」なのかを明確に切り分ける視点が重要です。そして、必要な情報提供と適切な作業区分によって、制作者との合意形成を図ることがスムーズな修正対応が可能となります。
CMSの仕様制限によって修正ができないケース
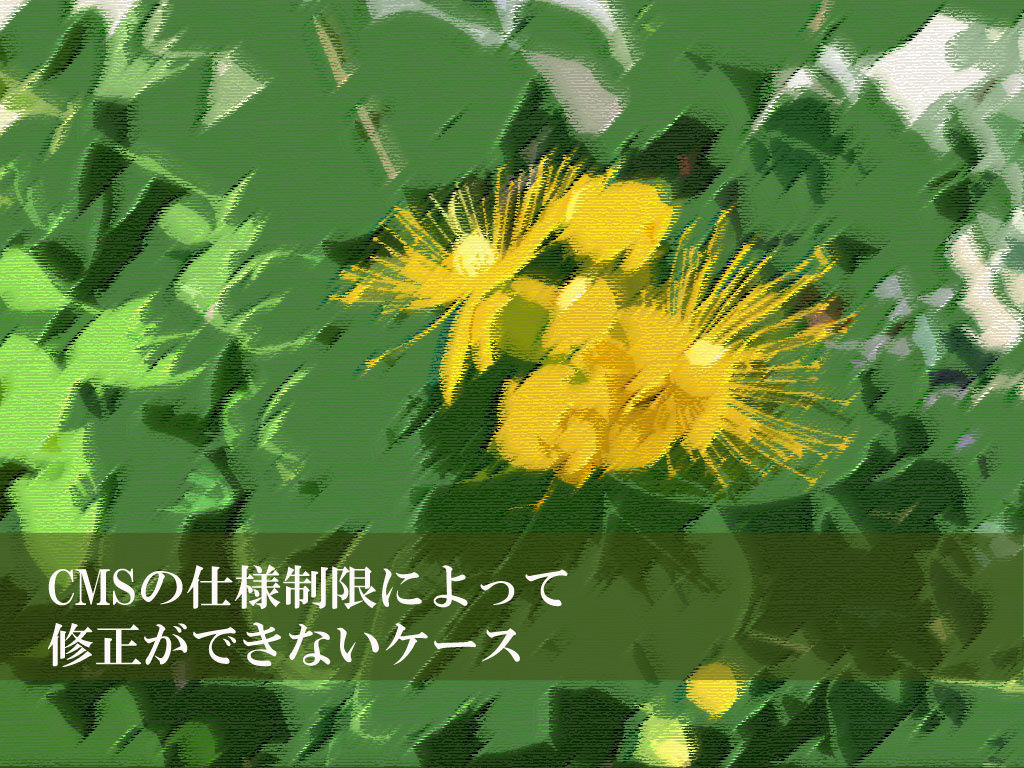
多くの企業や個人事業主が利用している「サブスク型ホームページ」や、独自CMSによる構築サイトでは、ユーザーに付与されている編集権限が極端に制限されていることがあります。具体的には、画像の差し替えや文章の修正はできるが、レイアウトの変更やメニュー構成の変更、フォーム項目の追加などは一切許可されておらずシステムの深部にはアクセスできない仕様となっていることがあります。このようなサイトでは、仮に外部の業者に依頼しても、サーバー情報や管理画面の制限により作業が行えないため、修正そのものが技術的に不可能という判断になります。
この場合の対応策としては、現在契約しているCMSの運営元に対してカスタマイズ可能なプランへの変更を打診するか、WordPressなどのオープンソースCMSへの移行を検討することが現実的です。将来的に柔軟な運用を想定するなら、カスタマイズ性の高い環境へ段階的に移行することが望ましいでしょう。
古い技術やサービスを利用していて対応が困難なケース
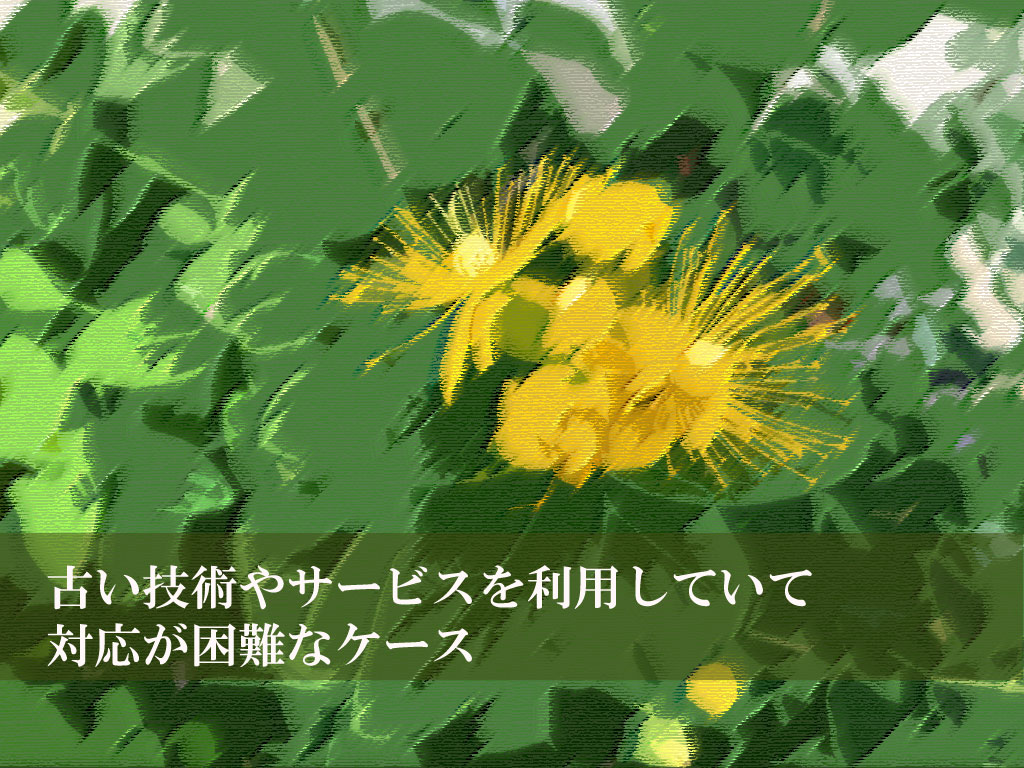
Flashコンテンツを使用していたり、サポートが終了したJavaScriptライブラリ(たとえばjQuery 1.x系)に依存しているサイトの場合、現行のブラウザやサーバー環境では正常に動作しないケースがあります。こうした旧式の技術に依存したページの修正は、セキュリティリスクが高く、再現性も低いため、制作者側が対応を断るケースがあります。無料の外部サービスに依存した表示(たとえばGoogleマップの古い埋め込み方式や、YouTube APIの旧バージョン)なども、既に仕様変更が行われており、現在では使用できないことがあります。これらは、もはや「修正」では済まず、「別の技術で置き換える」必要があり、一定の制作工数が発生します。
このような場合には、旧技術の撤廃と現行仕様への再構成を前提とし、移行計画と予算を立てたうえで依頼することが、解決への第一歩となります。
コードが破損しており、修正不能な状態になっているケース
過去に自社内でHTMLやCSS、JavaScriptなどのコードを独自に変更した結果、画面が崩れてしまった、リンクが動作しない、画像が表示されないといったトラブルが発生し、修正依頼が寄せられることがあります。しかしこのとき、コードが部分的に破損していたり、元の構造が残っていなかったりする場合には修復が極めて困難になります。特に、WordPressサイトにおいてテンプレートファイルやテーマのための関数、JavaScript系の記述を意図せず改変したことで、ページそのものが表示されなくなるといった障害もあります。このようなケースでは、単なる「修正」では済まず、再構築やテンプレートの再設計が必要になるため、修正ではなく「リニューアル案件」として扱われ、通常のスポット対応では受け付けられないことがあります。事前にバックアップがあれば復旧は可能ですが、そうでない場合は、現状のコードを読み解きながら対応可能な部分を特定するか、類似デザインでゼロから再構築を行う必要があります。これに備え、常時バックアップ体制を整えておくことが重要です。
デザイン的・構造的に非効率なサイト設計になっているケース
見た目が整っていてもホームページの内部構造が非効率に設計されているケースでは、小さな修正でも大掛かりな作業になることがあります。典型的なのが、CSSが統合管理されておらず、ページごとにバラバラにスタイルが記述されているようなケースです。このような設計では、一箇所の修正が他のページに影響を及ぼす可能性があり意図せぬ崩れや不具合を引き起こす恐れがあります。また、スマートフォン非対応(レスポンシブ未対応)の旧サイトなどでは、レイアウト変更が非常に困難であるため、「この部分だけスマホ対応してほしい」という修正依頼に対応できないことがあります。
こうした場合は、修正よりも全体的な見直しを前提とした構造改革型のリニューアルを提案されることが一般的です。特定のレイアウトや表現を無理に変えようとするのではなく、「新しいデザイン方針に沿ったテンプレート再構築」として依頼内容を整理し直すことで、制作者側も対応可能な状態になります。
修正対象のソースが提供されていない、またはアクセスできないケース
よくあるのが、「他社が制作したサイトを修正してほしい」という依頼です。このとき、制作当時のソースコードやFTP情報、CMSのログイン情報が提供されていない状態では、第三者のWeb制作者でも中身にアクセスできず修正しようがないという状況になります。また、管理画面のログイン情報はあっても、サーバーにアップロードされたファイル群にアクセスできない場合、PHPやCSSなどの直接修正が行えず、期待されたレベルの対応ができないことも多々あります。
こうした状況を避けるためには、サイト制作時に納品データの所有権を明確にし、FTP情報やサーバーパネル情報、CMSの管理者権限などをしっかりと引き継いでおくことが非常に重要です。もし引き継ぎが行われていない場合、現運営会社との交渉を通じてデータの受け取りを求める必要があります。